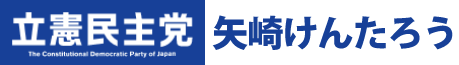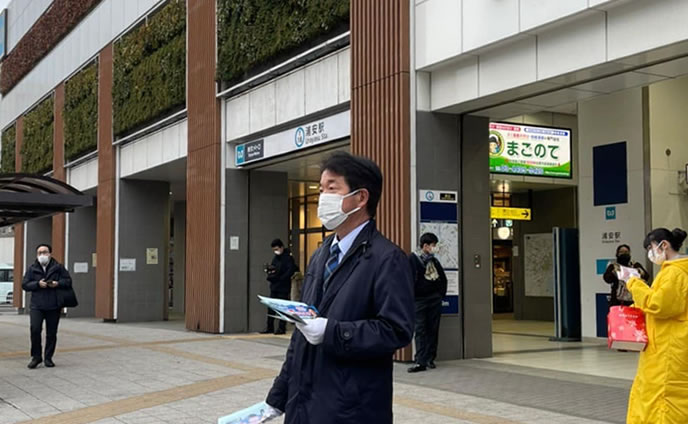今年度最後の文教常任委員会が3月13日に行われ、「県立高校学区撤廃について」「農業高校の生産物売払収入について」などの質疑をいたしました。以下内容を抜粋しご報告いたします。
◆◇◆県立高校の学区について
教育機会の平等と高校の特色化
公立高校の学区制度は、進学校や伝統校、スポーツが強い学校など、特色があって人気のある学校への生徒の集中を避けること、都市部と群部の学校の生徒数の平均化を図ること、受験競争を緩和することなどを目的に取り入れられた制度です。千葉県では、1975~1977年に13区が定められ、2001年に9学区制に改正されました。
この学区制度を撤廃する動きが全国的に広がっています。住んでいる地域によって、生徒自身が行きたい学校を選べないのは、受験及び教育機会の不平等につながるという考えや、学区撤廃で高校間の競争が生まれ、特色化が進むという考えからです。

公立高校に進もうとする中学生を主人公に考えれば、進学の選択肢を広げる学区撤廃を積極的に議論・検討すべきと考えています。それにより、生徒が減ることを危惧するより、公立高校がより豊かな教育を行える場として、切磋琢磨する方向に目をむけて、高等教育の充実化を図っていくよう、引き続き提言してまいります。
◆◇◆農業高校の生産物売払収入について
意義ある実習に予算の拡充を
浦安にはなじみがないかもしれませんが、県内には、農業科のある高校が13校あり(うち1校は募集停止)、作物の生産技術のみならず、流通や栄養学など、農業の担い手として必要となる広範囲な教育を受けています。
その中でも、自分たちが育てたり加工したりした生産物を、実際に売却する実習は、消費者のニーズを知り、適正なパッケージングや価格設定をして、売り上げの管理をする重要な体験機会となっています。
その実習の売り上げ金額は、規則の関係上、一度県の歳費に繰り入れられ、特定財源として農業実習費にあて、各学校に配分されています。
ルール上、売却収入でそのまま自校の備品などを購入できないとのことですが、やりがいがある仕組みづくりを要望。こうした取り組みから、千葉の新たな産品が開発される可能性もありますので、予算を拡充し、実習内容の充実化を図っていくよう求めました。
◆◇◆子どもと親のサポートセンター
事業の継続を要望
昨年春に、請願の紹介をし、継続となった事業です。不登校に悩む子どもと親に、経験者たちが寄り添い、最終的に学校に戻れるようになるまで、サポートする事業で、私は意義あるものと考えています。
審議の結果、今年度は予算増額のうえ継続されていますが、担当課と利用者とサポートセンターの関係強化を図って来年度以降も内容をより充実しながら続けるよう、要望しました。

◆◇◆耐震化工事中の県立美術館で
千葉県立美術館開館記念特別企画展は平山郁夫展
千葉県内では、公共施設の耐震化工事が順次進んでいます。
2010年に、市内の高校生からメールをもらい、県立高校の耐震化に取り組んだのをきっかけに、公共施設の耐震化についても指摘してまいりました。少しずつですが、こうしてかたちになっていることに活動の手応えを感じます。
今回の委員会でも質疑しましたが、千葉市中央区にある、県立美術館も耐震改修工事中で、来春リニューアルオープンとなります。
美術館の開館40周年も同時に記念する企画展は、平山郁夫展。来年1月24日(火)~3月22日(水)の日程で開催されます。せっかく開催される企画展、より多くの人々に見てもらえるように県としても広報活動をしっかり行うように要望しました。
要望したからには、私自身ももちろん行きますが、浦安からの展覧会ツアーなども企画したいと思っています。来年のことですので、日程等はこれからですが、ツアーがあるなら行きたいと思われる方は、下記までご連絡をお願いします。詳細が決まり次第ご案内します。
平山郁夫(1930年6月15日 – 2009年12月2日)
仏教やシルクロード、世界の文化遺産などをテーマに描く広島県出身の日本画家。世界の文化遺産の保護、救済のため「文化財赤十字」構想を提唱し、その活動は世界でも高い評価を得ている。東京藝術大学の学長、日本人初のユネスコ親善大使、など多方面で活躍した。
千葉県立美術館
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-10-1
JR京葉線『千葉みなと』駅下車(徒歩約10分)